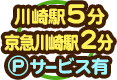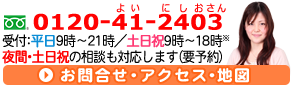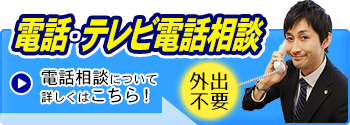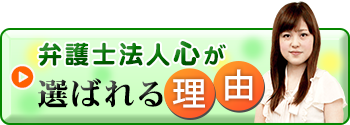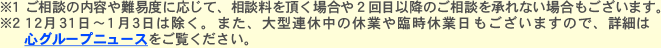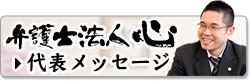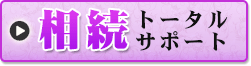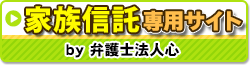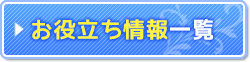遺言書の検認手続きをしないとどうなるか
1 検認が必要な遺言書
まず、検認が必要とされる遺言書は、法務局による自筆証書遺言書保管制度を用いていない自筆証書遺言と、秘密証書遺言だけであり、法務局に保管されていた自筆証書遺言や公正証書遺言の場合には検認手続きは必要ありません。
2 検認手続きをしないとどうなるか
⑴ 相続に関する手続きが進められなくなる
相続が発生し、遺言がある場合には、遺言の内容に従って、相続財産である預貯金の解約、不動産の相続登記、株式などの有価証券の名義変更などの相続手続きを行うことになります。
これらの手続きの際には、金融機関や法務局などで所定の書類等を提出する必要がありますが、検認が必要となる遺言がある場合、家庭裁判所における検認手続きの際に交付される検認済証明書の提出も求められます。
そのため、相続の実務においては、遺言書の検認手続きは必須であるということができます。
⑵ 過料に処せられる可能性がある
検認が必要な遺言書に封がなされている場合、検認手続きをせずに開封してしまうと、5万円以下の過料の処せられる可能性があります。
3 検認手続きの流れ
検認手続きは家庭裁判所で行われる手続きであり、ある程度の時間や手間がかかりますので、相続手続きを急いでいる場合には早めに行う必要があります。
まず、家庭裁判所に検認の申立てをする際には、遺言書のほかに、遺言者の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺言者の住民票除票または戸籍の附票を取得する必要があります。
家庭裁判所に検認申立書と必要書類を提出すると、家庭裁判所で検認手続きを実施する日時を知らせる、検認期日通知書という書類が届きます。
検認期日になりましたら、最低限検認を申し立てた方が家庭裁判所に行き、裁判官の立会いのもとで検認手続きが実施されます。
検認手続きは、特に問題がなければ数十分程度で終了し、手続きの内容が検認調書に記されます。
手続き終了後には、検認済証明書の申請をすることで、相続手続きに必要な検認済証明書を取得することができます。